『これって面白いね。』とか、『わー、おもしろーい。』とか、
そういった会話をゲームに限らず、私たちはよく耳にします。
しかし、その『面白い』という言葉が意味するところは、
いろいろな種類があって、曖昧なままではないでしょうか?
曖昧なままでは、どうすればいいのかわかりませんよね。
そこで、面白いゲームを作るためには、
まずは『面白い』という言葉の意味をはっきり理解しておく必要があります。
つまり、『どういうことが面白いのか?』を知っておく必要があるのです。
『どういうことが面白いのか?』がわかれば、目標は明確になります。
目標が明確になれば、目標に向かって力強く前進することができますからね。
目標とは?そう、『面白いゲーム』を作ることです。
では、『面白い』とは一体、どんなことを指すのでしょうか?辞書で調べてみます。
おもしろ・い 【面白い】
(1)楽しい。愉快だ。
(2)興味をそそる。興味深い。
(3)こっけいだ。おかしい。
(4)(多く、打ち消しの語を伴う)心にかなう。好ましい。望ましい。
(5)景色などが明るく広々とした感じで、気分がはればれとするようだ。
(6)心をひかれる。趣が深い。風流だ。
三省堂「大辞林 第二版」より引用
|
今ひとつ、パッとしないところがあるので、別の辞書でもう一度調べてみます。
おも‐しろ・い【面白い】
(1)興味をそそられて、心が引かれるさま。興味深い。
(2)つい笑いたくなるさま。こっけいだ。
(3)心が晴れ晴れするさま。快く楽しい。
(4)一風変わっている。普通と違っていてめずらしい。
(5)(多く、打消しの語を伴って用いる)思ったとおりである。好ましい。
(6)風流だ。趣が深い。
小学館「大辞泉」より引用
|
大体、意味を理解できたと思うのですが、さらに別の辞書でもう一度調べてみます。
おも−しろ・い 【面白い】
(1)笑いたくなる気持ちになる。滑稽である。おかしい。funny
(2)退屈しない。楽しい。愉快だ。enjoyable
(3)魅力があって、心を引かれる。興味深い。pleasant
(4)望ましい。満足できる。favorable
講談社「日本語大辞典」より引用
|
もうほとんど、面白いとはどういうことか理解できたと思います。
そこで、上記の面白いを7つに分類して、面白いゲームを下記のように定義します。
| 面白いゲームの分類 | どういったゲームか? |
| A.単純明快なゲーム | 楽しいゲーム。愉快なゲーム。 |
| B.頭を使うゲーム | 退屈しないゲーム。快く楽しいゲーム。 |
| C.波及力が強いゲーム | 望ましいゲーム。満足できるゲーム。 |
| D.教育的要素のあるゲーム | 興味をそそるゲーム。興味深いゲーム。 |
| E.思わず笑ってしまうゲーム | 滑稽なゲーム。おかしいゲーム。 |
| F.現実ではあり得ないゲーム | 一風変わっているゲーム。趣が深いゲーム。 |
| G.素材が素晴らしいゲーム | 魅力があって、心を引かれるゲーム。 |
あなたが作るゲームに上記の7つの面白さがあればあるほど、
そのゲームは必ず面白くなり、ヒットするはずです。
以下、次の節から各々の面白さについて説明していき、
同時に、どうすればそのようなゲームを製作できるかの方法論を述べていきます。
単純明快なゲーム、それは一体、どういったゲームでしょうか?
それは誰にでも理解できる面白さのゲームのことです。
例えば、赤ちゃんのガラガラという玩具があります。
手に持って、振るとガラガラという音がする玩具です。
赤ちゃんが楽しそうにこの玩具を振る光景が目に浮かびますよね。
つまり、ある反応に対して必ずある反応が返ってくる。
そういう一連の動作があるゲームが単純明快な面白いゲームなのです。
具体例をゲームで挙げるとするならば、例えば、スーパーマリオ。
Aボタンを押せば、マリオはジャンプし、ジャンプの音がします。
これはガラガラの面白さと全く同じ種類のものです。
逆に、ある反応に対して全く反応がないゲームは面白くありません。
ボタンを押しても何の反応もないゲーム、行動に対して何の反応もないゲーム、
遊び手はそのようなゲームを面白がって遊んでくれることはないでしょう。
つまり、ガラガラのような単純明快なゲームを作ることが重要なのです。
これは面白いゲームにとって、基本中の基本です。
ビートマニアに代表されるリズムゲーもまさに単純明快なゲームの代表です。
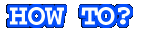
では、単純明快なゲームを作る方法とは?
1つの方法として、前もってゲームに制限を課しておくという方法です。
もう1つの方法として、後で複雑で無駄な部分を取り除くという方法です。
前もってゲームに制限を課しておくという方法とは、
ゲームを作る前から、設計する前から、あらかじめ条件を作っておく方法です。
例えば、方向キーと1つのボタンしか使わないゲームとか、
ゲームを始めて30秒以内に楽しめれるゲームとか、
自分が得たい結果の目標を立ててから、ゲームを作る方法です。
後で複雑で無駄な部分を取り除くという方法とは、
じっくりとゲームを洗練化させていくという方法です。
ゲームを作った後で、設計した後で、時間をかけて単純化させる方法です。
この方法では、テストプレイに時間がかかるという欠点があります。
ただし、本当に面白いゲームを作るためには絶対に必要な方法です。
私は、前者の『前もってゲームに制限を課しておくという方法』をオススメします。
後者も有効なのですが、取り返しのつかない状況に陥る場合があるからです。
特に、ゲームの規模が大きくなればなるほど、後者にはその傾向があります。
なお、前者の方法は目標に最短経路でたどりつくことができるので、
製作するのも精神的に楽です。何気ないことですが、非常に大切なことです。
前者の方法は、オリジナルのゲームを作る時に、有効な手法です。
後者の方法は、続編のゲームを作る時に、特に役に立つ手法です。
|
頭を使うゲーム、それはシミュレーションゲームやパズルゲームなどに代表されるゲームです。
頭を使うこと、知恵を絞ること、こういったことは面白いことであり、快感のあることなのです。
特に、頭を悩まし続けていた問題が不意に解けたときには、非常に心地よい気分になります。
逆にいえば、頭を使う必要のないゲームは面白くありません。
頭を使う必要のないゲームは、ただの単調な作業ですからね。
すぐに飽きてしまったり、退屈になってしまうことが容易に想像できます。
ただし、単調な作業はある一定のラインを超えると、面白くなることもあります。
RPGで経験値をえんえんと稼ぐことと梱包材のプチプチをつぶすことは似ています。
個人差があり、ゲームといえませんが、単調な作業は有効かもしれません。
そういった意味で、理想的なのは頭を使いながら、単純作業を行うゲームです。
テトリスなどはまさに頭を使いながら、単純作業をするゲームといえるでしょう。
テトリスが世界中で大ヒットした理由は、頭を適度に使うゲームだったからです。
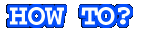
では、頭を使うゲームを作る方法とは?
1つの方法として、パズル的要素、論理的要素をゲームに組み込むことです。
パズル的要素、論理的要素は頭を使うことなので、ゲームが面白くなります。
ただし、パズルとゲームは違うことをはっきりと認識しておく必要があります。
パズルとゲームを混同すると、ゲームでなくなる可能性があるからです。
パズルとゲームの違いとは、解が存在するか、存在しないかの差です。
パズルのジグソーパズルには1通りの完成方法しかありません。これが解です。
一方、ゲームの野球には解がなく、得点で相手に勝つことが目的です。
このことがパズルとゲームの違いなわけです。
もう1つの方法として、トレードオフ、二律背反の要素をゲームに組み込むことです。
トレードオフ、二律背反とは、あっちが立てば、こっちが立たないということです。
つまり、複数の選択肢の中で1つしか選べないといった状況や
あることをすれば、あることができないといった条件のことですね。
例えば、ドルアーガの塔などは優秀なトレードオフ、二律背反のゲームです。
『剣を出せば、攻撃はできるが防御ができない。
しかし、盾を出せば、防御はできるが攻撃ができない。』
トレードオフ、二律背反とは、上記のようなシステムのことです。
なお、上級テクニックの剣を出しながら防御できるシステムも素晴らしいです。
|
波及力が強いゲームとは、多くの人に広まっていくゲームのことです。
ゲームの大きな目的の1つとして、人間同士の交流というのがあります。
言わば、人間同士の交流ができるゲームこそ面白いといえるのです。
この場合のゲームは、社会の潤滑剤としての役割を果たしています。
ゲームを通じて、人間同士が交流することができるのなら好ましいことです。
また、見知らぬ人とゲームを通じて、友人になれるのならば、素晴らしいでしょう。
また、ゲームとは参加人数が増えれば増えるほど、
ゲームの面白さが増大するという特性を持っています。
というのは、参加人数が増えれば、自由度や戦略が増える傾向があるからです。
ですので、いかに波及力の強いゲームを作るか?ということを考えることも重要です。
つまり、波及力が強いゲームほど、面白いゲームだといえるからです。
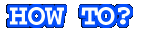
では、波及力が強いゲームを作る方法とは?
1つの方法としては一人では完結しないゲームを作ることです。
例えば、将棋やオセロや麻雀は一人では遊ぶことができません。
だからこそ、人間同士がお互いに誘いあって遊びます。
誘いあって遊ぶからこそ、そこに交流が生まれ、波及力が強くなるのです。
世界的大ヒットを収めたポケモンもまさに一人では完結しないゲームです。
ゲームのROMごとに、出現するモンスターを変えてくる趣向など、
まさに、交換を通じての交流を主眼に置かれて作られたシステムですね。
もう1つの方法として、ゲームに対戦要素、協力要素、観戦要素を入れることです。
例えば、野球やサッカーは、チームを組んで、チーム対チームで戦います。
チーム同士で戦うと複雑な展開になり、結果が全く予測できなくなります。
結果が予測できないからこそ、ゲームを遊ぶ価値がある面白いものとなるのです。
さらに、その試合を観戦する人が加われば、さらに面白いものになります。
他人のプレイを観戦することができるのならば、上手い人のプレイを真似ることで
ゲームの層が厚くなっていきますし、意見や感想を述べ合うことができるからです。
|
教育的要素のあるゲームとはためになったり、役に立つゲームのことです。
そのようなゲームであれば、多くの人は興味や関心を持ってくれます。
人間は何かを知ることに対しての欲望を持っています。
言わば、人間には知的好奇心というものが必ずあります。
その欲望を満足させることができれば、きっと面白いゲームになるでしょう。
教育的要素のあるゲームで大事なことは、新鮮な体験です。
既に知っていることでは多くの人に興味や関心をもってもらうことは難しいです。
ですので、二番煎じではない何かをゲームに組み込むことが重要です。
ゲームの優れた長所として、遊び手の意志決定によりゲームが進行するというのがあります。
この『遊び手の意志決定』を有効に活用することによって、高い教育効果を引き出せるでしょう。
ですので、教育的要素はゲームのどこかに組み込むことを強くオススメします。
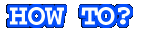
では、教育的要素のあるゲームを作る方法とは?
正攻法でいって、それは学問的な内容を参考にするという方法です。
学問的な内容といっても、別に難しいことを題材にする必要はなく、
誰にでも分かる小学生程度のかんたんな内容で十分です。
というのは、ゲームとは簡単でありながら、奥が深いゲームが最も良いからです。
小学生の授業の科目では、国語、算数、理科、社会などがありますが、
このような教科の中から選んで、ゲームを作るのも面白いかもしれません。
例えば、もじぴったんというゲームは国語の要素をもったパズルゲームといえます。
逆に、多くの遊び手は手軽に、簡単に、わかりやすいゲームを楽しく遊びたいので、
あまりに難しい題材をゲームにしても受け入れられないという可能性があります。
簡単でわかりやすい題材の方が多くの人に受け入れられやすいということです。
|
面白いゲームといえば、当然、思わず笑ってしまうゲームともいえます。
にこっと笑顔になるゲーム、腹を抱えて笑ってしまうゲーム、そのようなゲームは面白いです。
ゲームの役割の1つは娯楽として目的がありますので、このことは軽視できません。
人間は笑うことでストレスを解消することができます。
もし、ゲームを遊ぶことによってストレスを解消することができるのなら、
そのゲームには価値があり、役に立つといえるでしょう。
また、笑ってしまうことで、人間は楽しい気分になることもできます。
すこし嫌なことがあっても、このゲームを遊べばいい気分になれる、
多くの人はそういうゲームこそを望んでいるのだと思います。
この場合のゲームは、人間の精神を安定させる役割を果たしています。
ストレスの多い現代社会ですので、重要な役目だと考えられます。
その意味で、思わず笑ってしまうゲームを作ることは大切なことです。
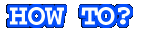
では、思わず笑ってしまうゲームを作る方法とは?
1つの方法として、自分が笑ってしまった場面を思い出して、
その場面をゲームにそのまま再現するという手法があります。
この方法は自分が笑ってしまったという体験があるので、
他人にも共感してもらえるという可能性が多々あります。
ゆえに、かなり有効な手法といえます。
もう1つの方法として、笑いを分析するという手法があります。
笑いというのは、ある一定の法則が必ずあります。
それは何度も漫才や寄席や落語を聞いていれば、気づくことです。
具体的にいえば、思わず笑ってしまう場面というのは、
風刺、パロディ、冗談、滑稽な様子、ナンセンス、シュール、繰り返し、落差、
などといった要素が必ず含まれているということです。
そういう要素を自分なりに工夫して組み合わせてみれば、
思わず笑ってしまうゲームを作ることができるでしょう。
|
現実ではありえないことは、胸がワクワクドキドキすることがあります。
簡潔にいえば、それは夢や希望である可能性があるからです。
だからこそ、現実ではあり得ないゲームは面白いのです。
逆にいえば、現実そのままのようなゲームは面白くありません。
現実で体験できるようなことはゲームで楽しむ必要がないからです。
現実の世界でできることは、現実の世界ですればよいのです。
SLGに代表される戦争を題材とするゲームは、まさに現実ではありえないゲームです。
もし、現実の世界で戦争を起こすとなると、多大なる破壊と浪費が生まれます。
ゲームという舞台で戦争ができるからこそ、そのゲームに価値があるのです。
ただし、ゲームが現実からかけ離れすぎると、また別の問題も噴出します。
社会の規範や道徳を無視しすぎると、ゲームに対して批判が巻き起こるかもしれません。
現実ではありえないゲームは魅力的ですが、その影響についても考慮しておくべきです。
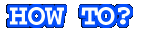
では、現実ではあり得ないゲームを作る方法とは?
それは空想小説や架空の漫画などを参考にすると良いかもしれません。
例えば、ジュール・ベルヌの海底二万マイル、藤子・F・不二雄のドラえもんなどの
多くの人に夢や希望を与えるような題材を参考にするとよいでしょう。
また、『こうであったらいいな。』とか『こういうことができたらいいな』などといった
自分自身で考えた夢や希望をゲームの題材にするのもいいでしょう。
ファンタジーという分野はまさにそういう夢や希望から出来上がった世界です。
他にも、現実でやろうとすると、手間や暇や労力が非常にかかることを
ゲームの題材としてゲームを作り上げることも有効な手法です。
例えば、何かの職業になれる、あるいは、何かの体験できるゲームは
まさに、現実ではあり得ないゲームの典型例です。
例を挙げるなら、電車GO!という列車のシミュレーターゲームがあります。
もちろん、現実の世界では、列車の車掌になることは大変な労力がかかります。
しかし、このゲームでならば、簡単に列車の車掌の疑似体験ができます。
だからこそ、このゲームは面白いのです。そして、ロングヒットしたわけです。
|
当然の話ですが、ゲームは様々な素材から作られています。
プログラム、デザイン、シナリオ、グラフィック、音楽などの素材でゲームは作られています。
その1つ1つの素材が素晴らしければ、ゲームの輝きと魅力が増します。
また、魅力があって、心を引かれるゲームは多くの人の関心を集めることができます。
多くの人の関心を集めることができれば、多くの人の話題になることは間違いありません。
そして、そういったゲームこそが面白いゲームといえるのです。
1冊の書籍で、1枚の絵画で、1曲の音楽で感動できるように、
素晴らしいゲームであれば、1つのゲームで感動することができます。
1つの最終的な目標としては、そのようなゲームを作ることではないでしょうか。
遊び手の心をギュッとつかんで、夢中になって時間を忘れて遊んでしまうゲーム、
おそらく、多くの人はそのようなゲームこそを面白いゲームだといってくれることでしょう。
ただし、全体としての作業量は膨大なものになるので、注意する必要があります。
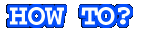
では、素材が素晴らしいゲームを作る方法とは?
これはもう地道に自分の実力を磨く以外にはないと言えます。
プログラムにしろ、文章にしろ、絵にしろ、音楽にしろ、長年の修練は必要です。
私のアドバイスとしては、自分の好きなことをやるのが成功のコツですね。
ただし、1つだけに特化してアピールするという方法があります。
あれやこれやと手を広げず、一点集中で一点突破を目指すのです。
この方法であれば、多くの遊び手に強いアピールができる可能性があります。
例えば、ファイナルファンタジーというゲームは、
シリーズを通じて、グラフィックにとことん力を入れるという伝統があります。
だからこそ、記憶に残るゲームになり、熱心なファンがついているといえます。
また、ゲーム自体としても、一点集中のゲームを作ると良いかもしれません。
ビートマニアなどに代表される音ゲーは音楽に一点集中することにより、
続編作を量産することに成功し、多くのファンを獲得することができたのでしょう。
|
| 
